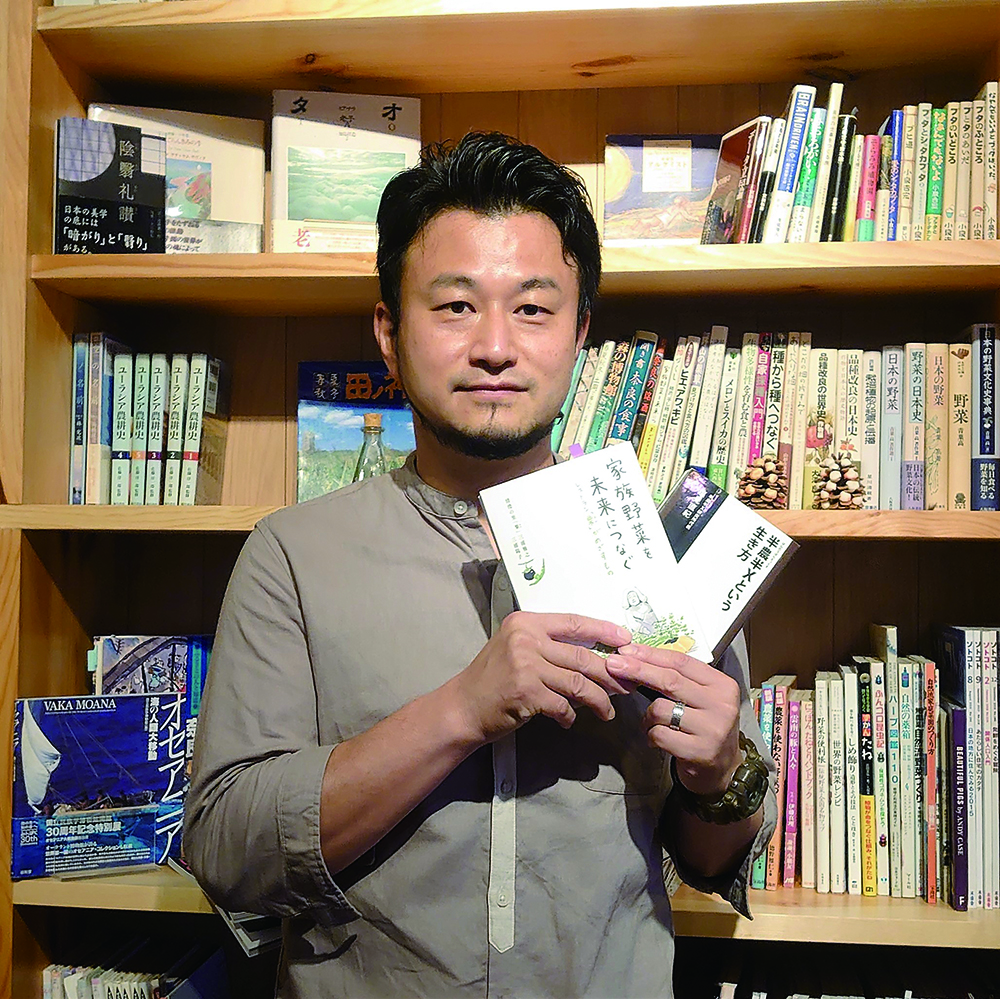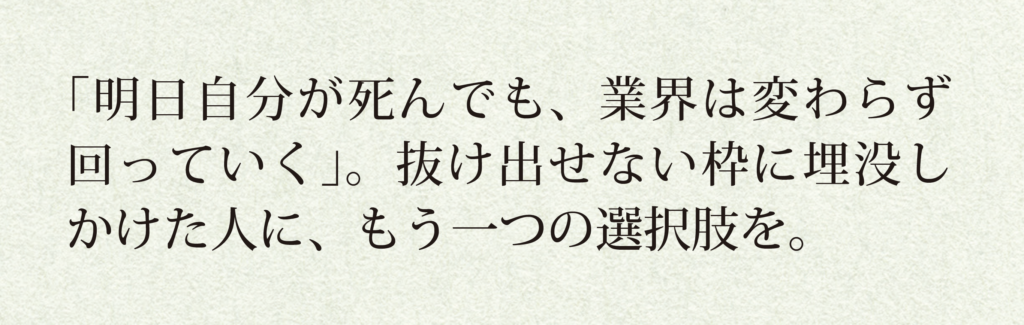この記事はさとびごころVOL.46 2021 summerよりの転載となります。内容は掲載当時のものです。
三浦雅之&阿南セイコがゲストをお迎えしてインタビューする連載
GUEST 玖村 健史さん(ARCH SHORENJI 代表・映像クリエイター)
HOST 三浦雅之・阿南セイコ
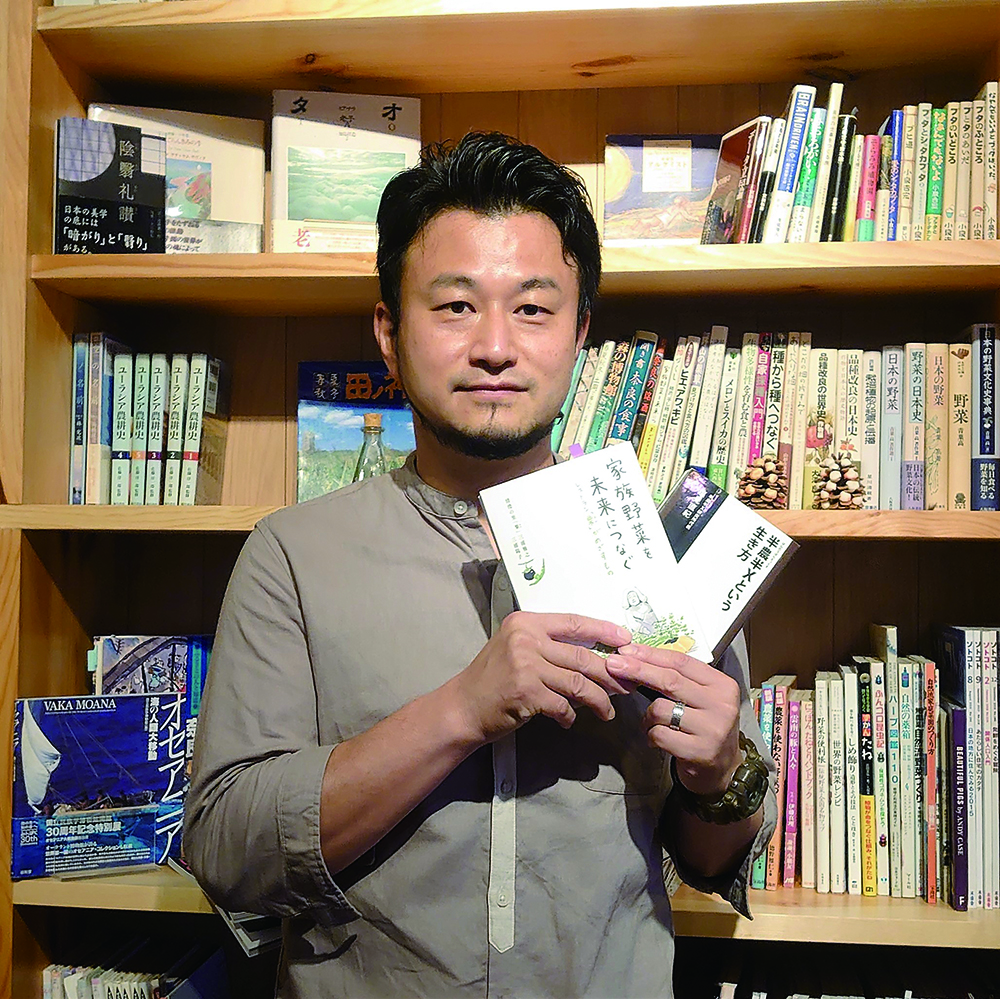 玖村健史さん。奈良県生駒市出身。ラグビーの名門大工大(現常翔学園)
玖村健史さん。奈良県生駒市出身。ラグビーの名門大工大(現常翔学園)
高ラグビー部OB。東京の広告業界で活躍したのち、関西で飲食業を経験し、独立。
2020 年より映像クリエイターを兼業。
コロナ禍の中、店舗の移転
阿南:玖村さんは名張市の青蓮寺湖の近くでレストランを経営されていましたが、昨年10月少し近所の場所に移転され、現在はスイーツ中心にカフェを展開されるかたわら、映像クリエイターとしても活躍されていますね。また、最近は山添村でお米づくりもされるようになりました。そのあたりのいきさつを伺えたらと思っています。
三浦:玖村さんとは長いお付き合いです。理系脳、文系脳、気配りセンサー、心の体力、元ラガーマンなので文字通りの体力、すべて持っておられる感じ。
玖村:米づくりは、母方の実家が山添村だった縁でコロナ後に始めました。幼い頃、学校が長期休みになる度に帰っては、思いっきり野山で遊んだ村です。
阿南:コロナ禍でいろいろと激動があったと思いますが、いかがでしたか。
玖村:当時は営業のスタイルを通常からビュッフェ形式に変えて一年半。予想以上に繁盛していましたが、せっかく作った料理が残り廃棄する量も多く、70席あるホールをひたすら回す作業に追われる日々に疑問が生まれ始めていました。しかし、変えたばかりだし、せっかくファンもできているし、あと1年頑張ろう…と思った矢先のコロナでした。業態を変える言い訳が来た!とでもいうか。ある意味、コロナのおかげで一旦立ち止まり、僕にとって「本当に大事なものって何なのか、考えることができました。それは、家族(ヤギを含む)と従業員。ここが守れたら他のことは覚悟しようと。そのために、ぐっとミニマムにして、忙殺されずに納得のいく形で食べてもらう業態にしました。僕と妻は飲食店に関してはある程度やりきった感がありましたので、これからは、8年間も店に勤め続けてくれてパティシェでありながらもホール業務に重心を置かざるをえなかった一人と、後から加わってくれて、おしゃれなカフェをやりたいという一人、この二人がやりたいと思うことをもとに形にしたのが今の店です。
僕の元来の経営理念は「過疎地域活性化の新しいモデルとなり、地域とともに発展していくこと」「都会と田舎を結ぶ親しみやすい中継地点になること」なのでそれだけはぶれずに。
三浦:めっちゃわかります。ピンチをチャンスにですね。
玖村:周囲のみなさんに可哀想がられるんですけれど、へこみながらも結果オーライ。僕だけが元の店の建物に愛着があって戸惑いましたが、あとの女子たちは晴れやかそのものでした。
映像制作を始めたわけ
阿南:結果オーライとは、びっくりです。それで、ここから何故か突然、映像制作の活動を始められるんですよね? もちろん、東京で広告業界の仕事をなさっていたことは存じてますが…。その復活ですか。
玖村:実は僕、余興が大好きで。以前、三浦さんのパーティー(※)で、友人に編集をしてもらって映像コンテンツを作ったことがあるんです。その時は仕事にするとは思っていませんでしたが、自分で編集できたらなあと思っていました。
その頃すでに経営理念の実行のため、飲食店以外にも、名張で町づくりする関係者さんと交わり、フォーラムを開催するなどの活動をしてました。そこで、素晴らしい取り組みをしている共感できる人たちがいることがわかっていたんです。歴史から勉強していて、ちゃんと未来のことも考えて、自分はこうしていきたいという意思を持って。でも、なかなか周りに理解されにくいんです。「あ、この人たちをもっと市内外に伝えていきたいな。そうしないと埋もれたまま一生を終わっていくな」と。そんな中で、ユーチューブなどの発信ツールも整ってきていますので、彼らの存在を伝える技術を身に付けたいと強く思ったのが、映像制作をスタートした動機です。飲食店を始めたのも、シェフとして大成するためではなくて、自らが田舎での幸せな生活のモデルになり、都会と田舎の中継地点になるため。結局僕らは、お店にいて「ここはいいところだよ。来て来て」と思っている状態。このまま、こうしていても目指すところには届かないと思いました。それって、15年前の自分を助けたいということと重なるんですけども。
※ 2018 年 第47 回日本農業賞 食の架け橋部門にてプロジェクト粟 大賞受賞、第57 回農林水産祭 多角化経営部門にてプロジェクト粟 内閣総理大臣賞受賞の祝賀パーティー
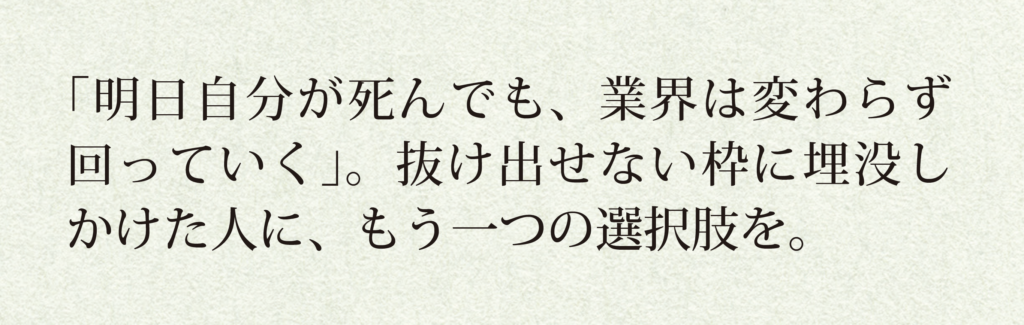
夢で見た緑の小道
三浦:広告業界におられた時ですね。
玖村:はい。当時を振り返ると、都会という枠の中では、このレールからはずれたら死ぬしかないみたいな感覚に陥っちゃうんですよね。僕は山添を知っていたけど、知らない人はそこで死んでいってるんです。その時、「名張があるよ」と思ってもらいたい。「一度、来てみたら」というのを作りたい。
市にも働きかけ、「関係人口を作ったうえで、半年間は移住支援する」という案を出したりしています。サポートがある間に生きる方法を見つけましょうと。いきなり実現は無理ですけど、それぐらいやらないと、アピールできないと思っているんです。
広告の世界って、糸井重里さんなどの時代は創造的な要素がありました。でも、時代が変わり、費用対効果の問題だけが中心になってくると、価格訴求的になっていきます。20代後半からはディレクター的な立場になりましたが、最終的にプレゼンに勝つためのあらゆる交渉や手配に終始していました。大手の競合相手は荒い手も使ってきます。それでも勝つために、嫌なことや人を貶めることもして、広告をしているのか何をしているのかわからない状態になっちゃう。
あるとき、本当の話ですけど、満員電車からバスに乗り継いでの帰り道、「あ、俺が明日死んでも世の中何も変わらないよな」って思ったんです。もちろん親や親戚は悲しみますけど、広告業界の歯車は全部回っていく。子供の頃からラグビーをして精神と体を鍛え、一応受験も頑張って、何かを目指してきたのはこんなことのためだったのか。しかも、じゃあその仕事をやめれるかといえば、「家族や子供のためにはやめられない」。そう言いながら育てた子供は、また同じ連鎖を繰り返すのだろうか…そう思うと、絶望感しかなかった。その頃、1週間くらい連続で、山添の夢を見たんです。それが、田んぼとかじゃなくて、普通の草ぼうぼうの小道なんです。小道の緑が見えて、自分が涙しているという夢。間違っているんじゃないかと思ったんです。大事なものが本当はあったのに、どこかで見失ってわからなくなってるんじゃないかって。軽井沢へ誘われて行ったとき、気づいたことがあります。かっこいいからとかよりも、やむにやまれない気持ちを浄化しに来ているんだと。明治神宮も、駐車場代や入場料金を払って、緑の中に浸かりに行ってるんです。緑がちょっとだけあるカフェがバカ流行りします。浄化したいんですよ。なんと、生きにくいことかと…。「久しぶりに田舎に帰ってみようかな」 と思いました。
そして東京を離れ、その後独立した場所は山添村から車で20分。僕にとっては、そこには田んぼがあった。家族や親戚が集まり同じひとつの仕事を手伝い、絆が生まれ、祭りがあった。
今再び山添村の田んぼで米づくりを始めています。そこで今回、三浦さんに聞きたかったことがあるんですけど、三浦さんの場合は米ではなくて種だったんですよね。それは何故なんですか。
三浦:主食という視点で考えたら日本は稲すなわち米ですよね。 国によってはそれがとうもろこし、小麦、じゃがいも、里芋だったりします。 「それぞれの地域の文化を成り立たせているもの」とは何かを考えた時、 「和食〜日本の伝統的な食文化」がユネスコ無形文化遺産に登録されたことからも想像できるように、米と共に地域の食文化を生み出しているものとして伝統野菜が欠かせないということに気づいたのです。
玖村:そうかー。そこまで考えてるってすごいなあ…。
三浦:玖村さんの人生を半農半X的に考えると、 農に加えて、カフェオーナーと映像クリエーターという二つのXの相乗効果で 人と地域を、そして都市と農村を紡いでいこうとされています。では最後に、これからの話を…。
これからの僕にできること
玖村:まだまだ勉強中の米づくりですが、今の田んぼの周辺は全て、後継者がいません。じゃあ僕しかやらなくなったらどうなるの?と思う。そんなとき、都会で農業に興味がある人に「来れないときは僕がやるから一緒にやってみましょうか」と言えたらいいなと。それを信頼できる人たちとやっていけたら、むちゃくちゃ楽しそう。でないと、閉鎖的な山村にいきなり都会の人が来られても拒絶されるのは予想できます。僕のような外から入ってきている人間が受け入れないと。映像に関しては、今の仕事がもうちょっと落ち着いたら、移住者とか、田舎をテーマに活躍している人にロングインタビューしたものを発信して見てくれる人が増えたら意味があると思うので、真剣に構想しています。さとびごころ、七つの風の動画版みたいになれたら(笑)
阿南:ぜひやってください!
玖村:三浦さんにインタビューするときは何を聞きたいか、もう考えているんですよ。知られざる時代の部分(笑)。
三浦:信頼する玖村さんでしたら、秘密でも何でもお話しさせていただきます(笑)。

取材を終えて。
清澄の里粟の閉店時の場をお借りしてインタビューした後は、三浦さんの愛妻陽子さんの手料理をいただくという僥倖に預かりました。三浦さん夫妻の著書『家族野菜を未来につなぐ』は玖村さんのバイブルとなっています。
さとびごころVOL.46 2021 summer 掲載