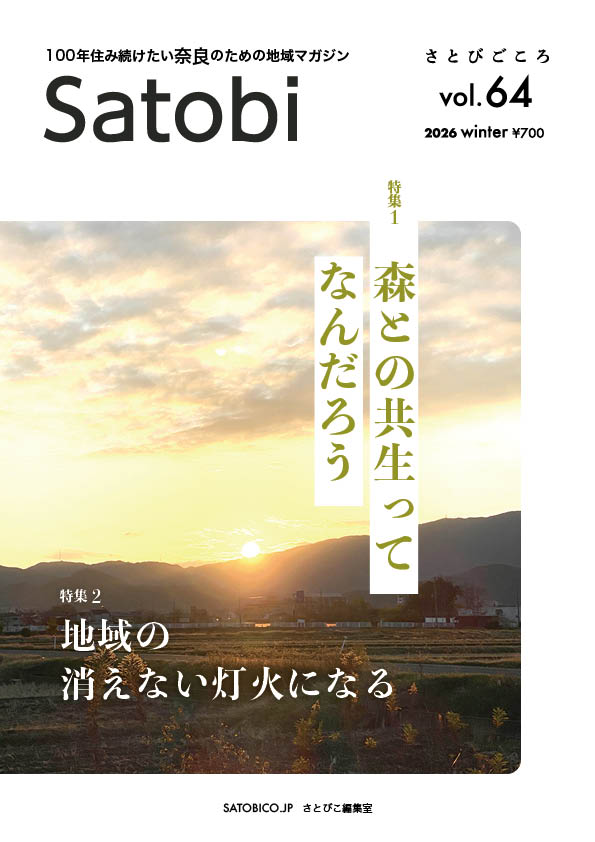さとびごころ63号「身の丈しごと人に会いました」で取り上げました小林孝恵さんの津軽こぎん刺し。紙面ではこぎん刺しについてあまり書けなかったので、ここで追記させていただきます。
by戸上昭司(身の丈しごと研究家)
(編集部より。戸上さんの整った文章、読ませてくれます!奈良との関係にも触れられていますので、ぜひぜひ、最後までどうぞ。)
私は、孝恵さんのインタビューの間、「これが農民芸術というものかぁ」ということを考えていました。宮沢賢治の『農民芸術概論綱要』をご存知でしょうか。この書は、彼の数多の小説と違って短文であり、インターネットで検索すれば全文が読めます。この書は以下のような言葉から始まります。
※原文を、多少読みやすく書き換えています(旧仮名遣いの書き換え、漢字に差し替えなど)。
俺たちはみな農民である。ずいぶん忙しく仕事もつらい。
もっと明るく生き生きと生活をする道を見付けたい。
我らの古い師父たちの中には、そういう人も応々あった。
そして、この師父たちの時代と賢治の生きた時代をこう論じます。
かつて、我らの師父たちは、乏しいながらかなり楽しく生きていた。
そこには芸術も宗教もあった。
いま我らには、ただ労働が、生存があるばかりである。
宗教は疲れて、近代科学に置換され、しかも科学は冷たく暗い。
芸術は、いま我らを離れ、しかもわびしく堕落した。
賢治がこれを書いたのは1926年。一方こぎん刺しは、おおよそ1700年代後半に誕生し、1800年代に隆盛を極めるも、1900年前後に急速に衰退します。賢治は岩手県の生まれ育ちですから、こぎん刺しのことも知っていたかもしれません。賢治の言う農民芸術の盛衰と、こぎん刺しの盛衰の流れがぴったり符合するのは、果たして偶然なのでしょうか。こぎん刺しは、もしかしたら賢治が憂いた農民芸術の一つだったのかもしれません。
津軽こぎん刺しの誕生から衰退まで
江戸時代は、木綿がまだ全国に広く普及していたわけではありません。特に綿花が育たない北国では木綿は贅沢品の一種だったそうです。それでも、江戸時代に入り、流通が盛んになると、東北にも少しは木綿が入ってきていたようで、麻衣の裏地に木綿生地を使うなどしていたようです。しかし、江戸時代も100年以上過ぎた1700年代半ば頃、幕府や藩の財政逼迫や飢饉などの影響もあり、度々倹約令が出されるようになります。津軽藩(現・青森県の西部)でも木綿の着用が一切禁じられ、当時の農民は麻を着るしかありませんでした(麻は自家栽培していました)。しかし麻布は擦り切れやすく、保温性に乏しいため、北国の衣類としては不向きです。そこで農民たちが考えたのが、補強や保温のために、麻布の目を同じ麻糸で埋める刺し子です。これが「津軽こぎん刺し」の原型になります。
倹約令が緩くなってきて、木綿糸が入手し易くなると、藍染した麻布に白い木綿糸で刺すことが一般的になりました。色が映えることもあってか、女性たちは工夫を凝らし、次第に様々な模様を生み出していくようになりました。こぎん刺しの代表的な模様である菱形の模様は、1700年代後半に書かれた書物に既に登場しています。
明治に入ると(1800年代半ば)、木綿が自由に手に入るようになり、こぎん刺しは一気に全盛期を迎え、津軽女子でこぎんを刺さなかった人はいなかった、とも言われるほどでした。女性たちは、競い合うようにデザインに工夫を凝らし、自分で刺した晴れ着を着て村祭りに出かけ行ったそうです。しかし、1891年に東北本線(鉄道)が開通し、青森県でも木綿の衣類が自由に手に入るようになると、こぎん刺しは急速に廃れていってしまいました。
 津軽ごぎん刺しの例 出典・青森県観光情報サイト
津軽ごぎん刺しの例 出典・青森県観光情報サイト
生活文化としての刺し子
現代では、刺し子を趣味活動として始める人が多いと思われます(孝恵さんも初めはそうでした)が、当時の津軽地方では、刺し子は生きるための〈しごと〉です。女性は、5〜6歳から針を持ち、何枚もの刺し子の着物を作って嫁入りしたと言われています。刺し子自体も大変なおしごとなのだと思いますが、実は当時、刺し子の10倍大変な〈しごと〉が他にあったのです。それは生地である麻布づくり。麻布も自分で栽培して自分で布にするのです。4月に種を蒔き、初秋に収穫した後、糸にする作業が冬まで続きます。そして2月になってようやく麻糸が織り機にかけられ布になっていくのです。
当時の農民にとって、こぎん刺しの衣類とは、麻の種まきから衣類の完成までに費やされた膨大な労力のことを思うと、それはそれは大事な生活必需品だったのです。だからこそ、どんなに小さな布切れでも大切に取っておき、補修に使ったり、裂き織りにしたり、と最後まで無駄なく再利用されたのです。こぎん刺しも、着古されてくると二重三重に刺し綴られ、藍も何度も染め直しが行われました(藍もまた自家製で、集落の藍小屋で隣近所分まとめて染めていました)。
こぎん刺しの復活
1900年前後に一度途絶えかけたこぎん刺しが再び注目されたのは、1940年頃です。当時の民藝運動の流れの中から再発見されました。民藝運動の創設者・柳宗悦はこぎん刺しについてこう綴っています。
名も無き津軽の女達よ、よくこれほどのものを遺してくれた。
柳宗悦は、こぎん刺しが生活に即した「用の美」であると唱えました。
その後は、刺し子の伝統技法を生かしながら、近代的なデザインが次々に生まれ、作品にも多様性が生まれ、多くの作家が全国各地で生まれていきました。現在ではたくさんの図案集も発刊され、様々な創意工夫が施されて今に至ります。
こぎん刺しと奈良の関係
こぎん刺しは、元々は青森の文化であり、奈良はあまり関係なさそうですが、実は、現代のこぎん刺し文化を支える一旦を、奈良が担っていると聞くと驚きませんか!
奈良で麻といえば、そう「蚊帳」です。現代において、本当に伝統的な津軽こぎん刺し(目の粗い藍染の麻布に白い綿糸を刺すこと)を行いたければ、その生地は奈良でしか入手できない、と言われているのだとか。孝恵さんもこの会社から購入しているそうです。その名も、株式会社三広織布。
https://www.sanko-orifu.jp
(編集部より。HPのオープニングムービーに萌え萌えです!糸、織機、職人さん。ぜひクリックしてみてくださいませ)
こぎん刺し用の生地を扱っている会社は、一般にはその生地に販売していないようなので、ご注意ください。けれども、こうして奈良の伝統文化と現代のこぎん刺しがつながっていることが、嬉しく感じられ、紹介させていただきました。また機会があれば、さとびごころで取り上げられるといいな、と考えています。
最後は、宮沢賢治さんに締めていただきましょう。
いまや我らは、新たに正しき道を行き、我らの美をば創らねばならぬ。
芸術をもって、あの灰色の労働を燃せ。
ここには、我ら不断の、潔く楽しい創造がある。
都人よ、来って我らに交われ。
【参考文献】
弘前こぎん研究所・監修、『津軽こぎん刺し:技法と図案集』、誠文堂新光社(2013年)
宮沢賢治、『農民芸術概論綱要』、青空文庫(https://www.aozora.gr.jp/)より
この記事は、さとびごころvol.63(2025 autumn) 内の記事「身の丈しごとびとに会いました」の続きの記事となります。冊子もあわせてお楽しみください。