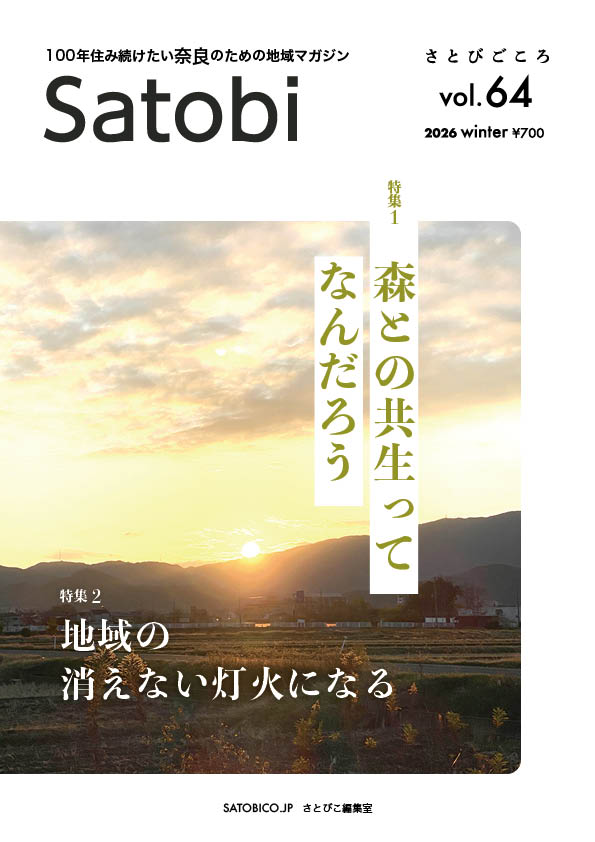選挙が終わりましたね。さとびでは、政治的な話題は扱わないことにしていますが、わたし個人は必ず投票します。自分で考え、決めて、意思表示するチャンスなので。今回の結果、みなさんはいかがでしたか。
選挙ポスターが並ぶのを横目に見ながら、さとびの発送や配達をしていました。作業は苦になりませんが間違えやすい性格なので「間違えそうプレッシャー」がはんぱないうえに、ざーーーっと機械的にできなくて、ひとりひとり気持ちをこめてしまうので時間がかかるにもかかわらず「もう発行してるんだから、早く届けないとプレッシャー」が重なり、しばらく他のことが手につかなくなります。これが年4回、定期テストのようにやってくるのです。それもやっと落ち着いてきました。
すると、畑活が楽しくなります! 告知に関係ないこんな記事を書くこともできます!
夏の畑活は、早朝一択。やることは見回りと草刈り、収穫少々。ベランダで種から育てたオクラを畑デビューさせたものが、成長中(上記の写真)。オクラは花が咲いてから数日で食べごろになり、それをすぎると固くて食べられなくなります。ですから、タイミングよく育ったところだけ、食べています。売らない畑活はのんきなもので、プレッシャーをしのいだあとで、畑でまたプレッシャーを背負わないことにしております。
本当は、毎日足音を聴かせてあげられる距離に、「自由にやっていいよ」という畑(エディブルガーデン)があったら…。その希望は目下のところ、引き出しの中に保管しておきますが。
さて、今日は自分のメモを兼ねまして。
畑活を始めた頃、さまざまなユーチューバーさんを訪問していました。知れば知るほど難しくなるので、ときどき情報の断捨離をして、現場主義に戻るのですけど、それでだんだんと今の自分に合ったスタイルが見つかってきたように思います。
そんなユーチューバーさんで、かの「わら一本の革命」で有名な福岡正信さんに学び、自然農法を実践されている方があります。自然農法というと、ストイックで難しいという印象を持っている人もあると思いますが、この方は哲学の部分を受け継ぎながら実践の中で技術をつかみとってこられたのかなと思って見ています。(ちなみに奈良では川口由一さんが有名ですね)
これより引用
農作物に病害虫(抗原)が侵入すると,農作物の体の中には抗体ができる。
たとえば,イネに『いもち病菌』という抗原が入ると,イネはそれを排除しようとして抗体をつくり,激しく抵抗する。この抗体のできた稲わらを籾殻温床内で60~70℃の高温発酵させると,いもち病菌は死滅して 抗体だけが残る。
この抗体を含んでいる発酵籾殻や稲藁を翌年冬期湛水田に投入すると,イネはこれを吸収・利用し,イネの体は強くなる。無数のいもち病菌が空中を浮遊していても,彼らはイネの体内に侵入することができなくなるのである。これは,紋枯病やごま葉枯病,小粒菌核病など,イネの病害のほとんどに適用できる手法である。
自然農法は 『自然のままに何もせず放っておくもの』と思われがちだか、これらは幻想に過ぎず、農業そのものが、自然破壊である以上自然からの厳しい審判が下る。稲しか生えていない田んぼ、茄子しか生えていない畝、ニンゲンが作った圃場という不自然な空間 、その不自然さをただしに 病害虫が飛んできて作物を犯す。これは人類が農業というパンドラの扉を開けてから今日までかかえ続けてきた悩みであり、宿命なのである。
それらを農薬で無かった事にするか、先に書いたように自然の摂理で農作物を守るかの選択が問われる。どちらもニンゲンの叡智からうまれた技術ならば出来るだけ他者を傷めず 環境を汚さず、作物そのものを穢さない方法を採用したい。
それが自然農法。
病害中に犯されたたった一本の稲藁から抗体を作り、農薬の必要としない田んぼを作る。これが自分の『わら一本の革命』である。
農薬や化学肥料を使った農業を全否定はできなくて、そのおかげで「農業」があることも認識していますが、自然農や自然栽培でプロ農家をされている方は、なおさらリスペクトしかない。「業」ではなくて、生活の一部として、自給目的の畑くらい無肥料無農薬でやりたいですよね。
ところで、わたしはハーブや雑草(野草というべきでしょうか)をしょっちゅう使っているのですけど、これらの薬効というのも、植物が生き延びるために体内で作った成分なんですよね。自然そのままに生きているものでも、抵抗力がないと種を残せないんですね。
ウイルスや、苦しいこと、つらいことも同じで、ないほうが平穏でいいんですけど、全くなかったら何の能力も抗体も作れないことになってしまいますよね。適度な風邪やストレス、そのときは辛いけど、きっと自分の力になっている。。。
最近、ちょっと(自業自得で)ダメージを受けることがありましたが、必要以上に自分を否定しないで、現実を受け止めて、「だからどうする」ということをまたひとつ重ねるチャンスなんだと思いました。自然の摂理を思い出すと、いろんな場面で、どうしたいかが見えてくるように思います。
いや、わたしなんて、ほんとうに恵まれていて、鬱になることもなく、乗りきっていますけれど、仕事でメンタルや体を壊された方が、やっとの思いで「農」へ辿り着かれるケースがありますよね。その方たちは、メッセンジャーなんじゃないかなと思うんですよね。
自然というと概念が広すぎるように感じますが畑や田んぼや森も自然、自分の体も自然。自然とは摂理。環境と人間のバランスのとりかたを教えててくれます。
畑活をやっていて思うこと、追加。
わたしでさえ、小さくとも畑のある生活ができるということは、もう、ほんとに誰でもサルでも可能だと思うので、みなさん自分にとってのタイミングがきたと思ったら、ぜひぜひ、あたなの自給的農生活を始めてみてください。実際、さともだちの間では、農家ではないけれど農デビューする人があいついでいます。「田んぼを始めましたー」という人も、あちこちに出現。遊休地を借りて、経験者に学びながら、友人とグループを作って稲作りを始める人。同じく遊休地を借りて、自分で田んぼの管理をするのは限界があるから作業の多くを農業法人にオファーする人(収穫物は自給できます)。農業学校に通って、スキルを身につける人。最近では、さともだちの杉浦農園さんのたんぼ(御所市内)で稲活を始めた都市部の方がいらっしゃるとか。。。
やはり、じわじわと安心安全な食は自分で作るもの、という考えが浸透してきてるのでは。。。でも、それだけじゃモチベーションが続かないと思うんですよ。やっぱり、環境を守りたい、美しい風景や水源を守りたいという思いがあるから、自分のしていることが単なる「食い気」だけでなくて、違う満足感にもつながっているから、活動が楽しくなるんじゃないかなあと思います。いつか、そんな記事も作ってみたいかも。。。
わたしの畑も元は耕作放棄地です。放棄されていたときはセイタカアワダチソウを始めとする荒地に生きる野草(もはや木質化してるような)しかありませんでした。今ではホトケノザやヒメオドリコソウ、ハコベなどがたくさんやってきてくれています。
これからは、「とうとう今年でやめた」と決断される農地が増えていきます。そこに、ソーラーができるのか、廃棄物がつまれるのか、開発されるのか、農地として継がれていくのか、、、、
みなさんはどんな未来を望みますか。これからの農地は、農家さんだけでなく、安心安全な食べものを求める人たちもいっしょに、力を合わせていけたらと思うあなんでした。
 コンポストから芽生えて、実をむすんでしまったカボチャ
コンポストから芽生えて、実をむすんでしまったカボチャ
さとびごころvol.49 ( 2022 spring)特集 畑活デビューガイド
さとびごころ vol.61(2025 spring)特集 自分の食べものを育てよう