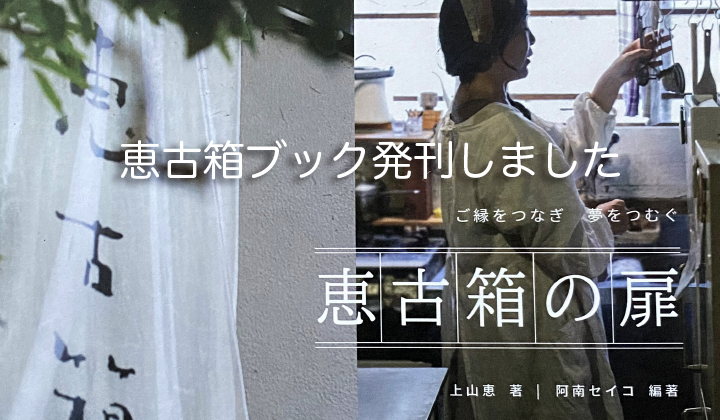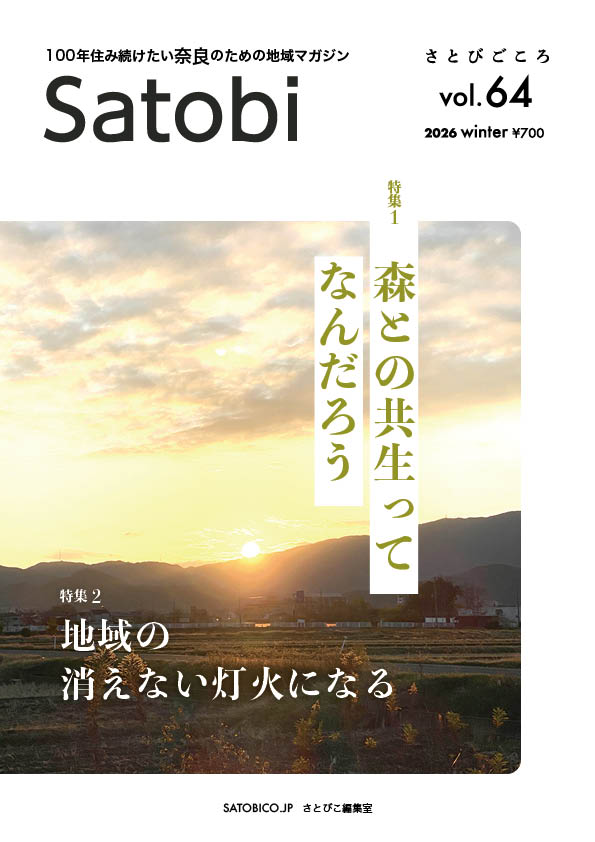秋号の取材で、葛城市にある 学校法人奈良学園 奈良文化幼稚園の角田道代園長先生にお会いしました。

「園に通う未来ある子どもたちのために、給食を変えたい」
「玄米と納豆をその日だけの特別メニューでなく、毎日続けたい」
「ハンバーグやスパゲッティなどはお家でも食べられるけど、
1日に一度、給食だけは、玄米で」
最初は先生の思いから始まり、何年もかけて努力され実現されたお話を伺ってきました。
そして、どんな変化があったのかも。
給食を変える以前に、角田先生の、教育哲学がありました。
「こどもたちは、遊びの中から学びます。この園で、おもいっきり遊びながら、育ってほしい」
角田先生は、園長に就任されてから、そのための環境づくり、体制づくりをされてきました。園庭には樹木が植えられ、焚き火コーナーやピザ窯もあります。木製の遊具は父兄の方が協力して作られました。教室のに壁は掲示板を設置せず、一面の木材がはってありました。給食の変化は、「こんな幼稚園だったから」ということが前提にあると思いました。


給食を変える夢は、簡単にはいきませんでしたが、先生の夢を思う情熱が変化を生んでいったことを教えていただきました。さとびは、共感し、嬉しくなり、こんな園があることを読者のみなさんにもぜひ知っていただけたらという想いをもって、記事を作ろうと思いました。
角田先生を初めて知ったのは、この夏、葛城市でお聞きした講演でした。先生の笑顔いっぱいの明るく生き生きとしたお人柄に心をうごかされ、「みらいの食を考える会.奈良.葛城」さまにご縁をつないでいただきました。
@mirai.shoku.nara.katsuragi
 角田道代園長とみらいの食を考える会.奈良.葛城の上山さん
角田道代園長とみらいの食を考える会.奈良.葛城の上山さん
給食を変えた園長先生のお話は、次号のさとび秋号で、お伝えします。
さとびごころ秋号は 10月10日発行します。さとびが届きましたら
角田先生のページ、チェックしてみてくださいね。
学校法人奈良学園 奈良文化幼稚園
https://www.narabunka.ac.jp/kindergarten/
角田先生のお話をききながら、かつて聞いた話を思い出していました。すでにさとびに関わっておりましたから、10年くらい前でしょうか、当時谷林業で開催されていたサロンに参加したときのこと。ゲストは村尾行一氏だったように思います。
このごろ、「森のようちえん」という言葉を聞くようになりましたが、以前はまだそんな取り組みをする人はほとんど見かけなかった頃のことです。村尾先生のお話から、ヨーロッパで森の幼稚園活動が始まった経緯や、大人の見守りかた、子どもたちの成長のことなどを知りました。
森のようちえんの発祥
1950年代にデンマークでエラ・フラタウ(Ella Flatau)という一人のお母さんが森の中で保育をしたのが始まりとされています。
大人はなるべく干渉せず、怪我や喧嘩なども、こどもたち自身で解決する力があることを信頼して見守り、安全面だけはきちんと注意する。それが森の中でこそ、実現しやすいのだというふうなお話でした。なぜ、それを思い出したかというと、角田先生が進めてこられた園庭に、樹木がたくさん植えられていたからです。すぐ隣を広い道路が通っており、田園と市街地がまざりあった環境にありながら、園庭は別世界に変貌しつつありました。これらの樹木がさらに成長したときのことを想像すると、5年後10年後が楽しみです。
子どもたちも、畑の野菜もそうですが、命あるものというのは自ら生きようとする力があり、まわりはそれをいかに適切にお手伝いするか、また、その恵みを調和を崩さずに受け取るかということが大切なのだといつも思います。自然というのは、本来は人間にとっては恐ろしいもので、今のように科学技術でコントロールすることはできなかったために、どうすれば自然とともに生きていけるかは切実なテーマだったはず。天地を離れて生きていくことはできない、その根本だけは、どんな時代になっても忘れないことが100年住み続けたい地域のために必要なことと思えてなりません(どこか遠くのほうでは、忘れている人が多いように思えるだけに)。
さとび最新号発売中
さとびごころvol.62 2025 summer
特集 雑草のある暮らしガイド(増ページ)
さとびこブックスの最新刊、好評いただいております。
ご縁をつなぎ夢をつむぐ 恵古箱の扉
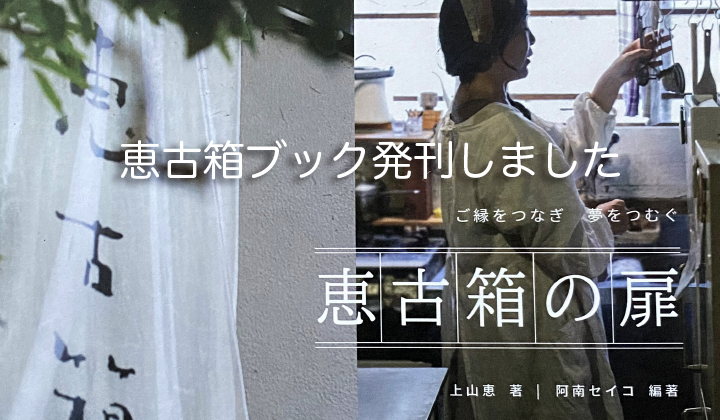
奈良県葛城市の人気古民家カフェ、恵古箱の店主メグさんこと、上山恵さんの15年間を見つめました。編集コンセプトは「あなたのおうちに恵古箱を」。恵古箱ファンのみならず、そのときどきの等身大の夢にむかって精一杯に、いつも挑戦しているめぐさんから、日々インスピレーションをうけとっていただけることでしょう。
メグさんは、今回の取材でお世話になった「みらいの食を考える会.奈良.葛城」の代表でもあります。ぜひインスタグラムをご覧ください。