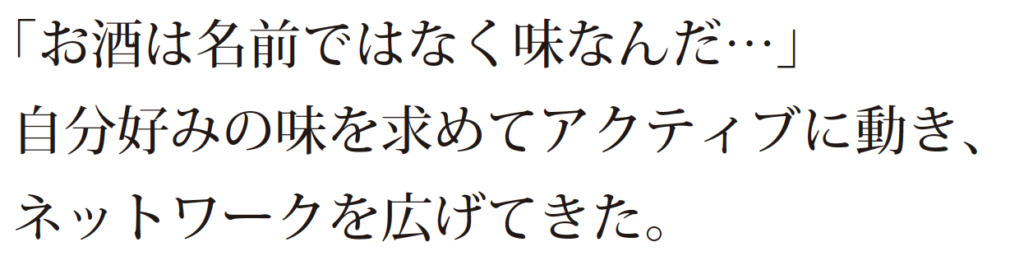この記事はさとびごころVOL.50 2022 summerよりの転載となります。内容は掲載当時のものです。
奈良の地酒ブランドの持続的成長を支えてきた地元の「小さな酒屋」の物語。
今回は、酒商のよりの店主、野依宏人さん(1963 年生)の物語です。
地酒との幸福な出会い
高度経済成長期が終焉を迎える1973 年、もともとサラリーマンであった野依さんの父親が「脱サラ」を決意し、廃業する店の権利を買い取って酒販店を営むようになった。その際には、店舗(近鉄菖蒲池駅付近)も屋号(山崎屋)もそのままの形で受け継がれた。
もともとは兄が家業を継ぐ予定であったため、野依さん自身は、家業への関心が薄く、大学卒業後、酒類とは無縁の業界に就職。そんなサラリーマン時代(1980 年代後半)に訪れた居酒屋(近鉄大和西大寺駅付近、すでに廃業)で口にした地酒「山鶴」(中本酒造店、生駒市)に衝撃を受けた。
「『目から鱗』でした。学生の頃にコンパとかで無理やり飲まされたもんですから、日本酒なんか大嫌いでした(笑)。その時に飲んだ『山鶴』は、きれいな感じのお酒で、それまで飲んでいた、べたぁとした、悪酔いする日本酒とはまったく違っていました。日本酒って良いなぁと思うようになって、それからちょくちょくそのお店に通うようになりました」。
その後、事情により家業を離れた兄に代わって、野依さんが家業に加わることになった。世はバブル景気に沸く1990 年のことである。その折の人生選択の背景には、「人に雇われるより自分で商売をやってみたい」という思いとともに、しばらく前に経験した地酒との幸福な出会いが大きな意味をなしていた。
 野依さん主催の酒の会(2013 年)
野依さん主催の酒の会(2013 年)
地酒専門店への業態転換
当連載において再三ふれてきた通り、1990 年代は「小さな酒屋」にとって大きな転換期であった。野依さんが先代に代わって店主となるのは1995 年のことであるが、それ以前から急激な環境変化を機敏に察知し、従来の経営スタイル(問屋経由の仕入れ、御用聞き・宅配)の見直しを図るとともに、酒蔵との直接取引の可能性を模索するようになっていた。
最初の直接取引の相手は、「花巴」醸造元の美吉野醸造(当時は御芳野商店、吉野町)であった。
「どこかでたまたま『花巴』を飲む機会があり、『これだ!』とピンときて、直接蔵に電話して交渉しました。すぐに取引がはじまりましたが、最初の頃は、このあたりでは誰も『花巴』を知らないし、なかなか売れませんでした。自分でチラシをつくって、配達先の各家庭に配りました。店のトラックに『花巴』のラベルを貼ったりして、それをみた人が買いに来てくれることもありました」。
このように野依さんがまさに地酒専門店への業態転換を図ろうとしていた時期、奈良県内ではすでに同様の先行事例がいくつかみられていた。その頃に登酒店の店主、登和成さん(野依さんより一回りほど年長)から誘いを受け、本誌第48号で紹介した酒販店情報ネットワークの勉強会(登酒店にて開催)に参加するようになった。また、その関係で、暁会(梅乃宿酒造の販売促進を目的とした地元酒販店のネットワーク)にも立ち上げ当初より参加している。
こうした「横の連携」のなかで、野依さんは、登さんをはじめとする先輩たちの取り組み(酒の会や蔵見学会の開催、メールマガジンの配信など)を参考にしつつ、顧客とのコミュニケーションの活性化に努めた。
登さんによれば、野依さんの第一の特徴は「ものすごくフットワークが軽いところ」にあるという。野依さんは、自ら飲食店への飛び込み営業を行なうなど、アクティブに動き、販路を開拓してきた。
また、「広いジャンルでネットワークをもっているところ」も野依さんの重要な特徴の一つである、と登さんはいう。この点に関して、野依さん自身はこう述べている。
「地酒をやりだした頃、地焼酎や国産ワインも同時にスタートさせました。その当時は焼酎ブームで、焼酎はいくらでも売れました。焼酎のおかげで、お店の名前が売れました。その裏で、地酒も一生懸命売っていましたので、それが後になって良かったのかなと思います」。
このように焼酎ブームの波にうまく乗れたことで、野依さんは、自店の業態転換(専門特化)を円滑に進めることができた。
2008 年には現在の所在地(大和西大寺駅付近)に移転し、それを機に店名も現在の名称に変更した。
2010 年には同じ奈良市内の観光客が多く行き交う三条通りに奈良三条店をオープン。店内に酒バーを併設し、好評を博した(2020 年初頭に惜しまれつつ閉店)。
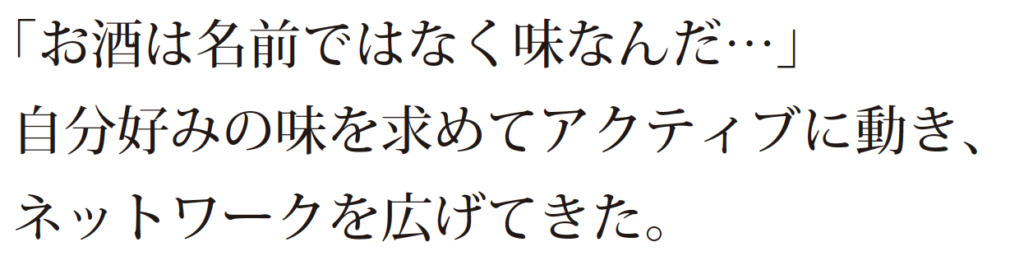
「小さな酒屋」の矜持
インタビューのなかで「酒販店経営者としてのモットー」を尋ねたところ、こんな答えが返ってきた。
「お酒は名前ではなく味なんだ、と思っています。地酒をやりだした頃から、有名な銘柄を追ってこなかったので…。いかに自分が気に入ったお酒を集め、お客さんにしっかり伝えていくかということなのかなと。
私はどちらかというと『濃いお酒』(注)が好きなので、うちで扱っている日本酒はそういうお酒に偏っています。うちみたいな店は、アパレルのセレクトショップみたいなものなので、店主は自分の個性を前面に出せばいいし、お客さんも自分の好みに合った店を選べばいいんじゃないかと思います」。
注・業界用語では「濃醇旨口」と表現される、米の旨みがしっかり出ている酒を指す。
「酒のセレクトショップ」は、登さんも好んで用いるフレーズであるが(本誌第44号参照)、何かしらのジャンルやコンセプトに特化した「小さな酒屋」全般に当てはまるキーワードであるといえよう。
現在、「酒商のより」が取り扱う地酒は97.7%が醸造元との直接取引によるものである。主力の地酒、地焼酎のほか、ワイン、ビール、ウィスキー、ジン、ラムなども豊富に取り揃えられており、こうした「脇役」陣も国内各地の「小さな醸造所」で造られる、個性豊かな商品ばかりである。
若い世代の造り手たちへのシンパシー
インタビューの最後に「これからチャレンジしたいこと」を問うたところ、「現状維持で精一杯…」という謙遜の一言の後、野依さんはこう述べている。
「これからの新しい可能性としては、若い世代の造り手さんたちが面白いなと思っています。
ツイッターとかでいろいろフォローしているんですけど、マイクロブルワリーみたいな酒蔵で、日本酒のもろみにお醤油を入れてみた、というようなことをアップしてはるんですよ。僕らの世代からしたら、こんなん考えられないですよ(笑)。これってクラフトビールの手法で、いろんなものをフュージョンして、新しいお酒を造ろう、ジャンルを取っ払ってしまおうという動き、税務署は大変でしょうけど(笑)、その辺が面白いと思いますね」。
このように、野依さんは、既存の枠組みを超越するような若い世代の造り手たちの動向に関心をもち、世代ギャップを越えて彼らにシンパシーを感じている。
還暦を目前に控えた今も、持ち前のフットワークの軽さとネットワークの広さ(それゆえの視野の広さ)は変わらない。今後、野依さんのアンテナには、どのような酒が引っ掛かってくるのだろうか。きっとそこにも個性豊かな人、蔵(醸造所)、土地の物語がたっぷり詰まっているだろう。
 野依さん主催の蔵見学会(倉本酒造(奈良市)、2019 年)
野依さん主催の蔵見学会(倉本酒造(奈良市)、2019 年)
さとびごころVOL.50 2022 summer掲載
文・河口充勇(帝塚山大学文学部教授)