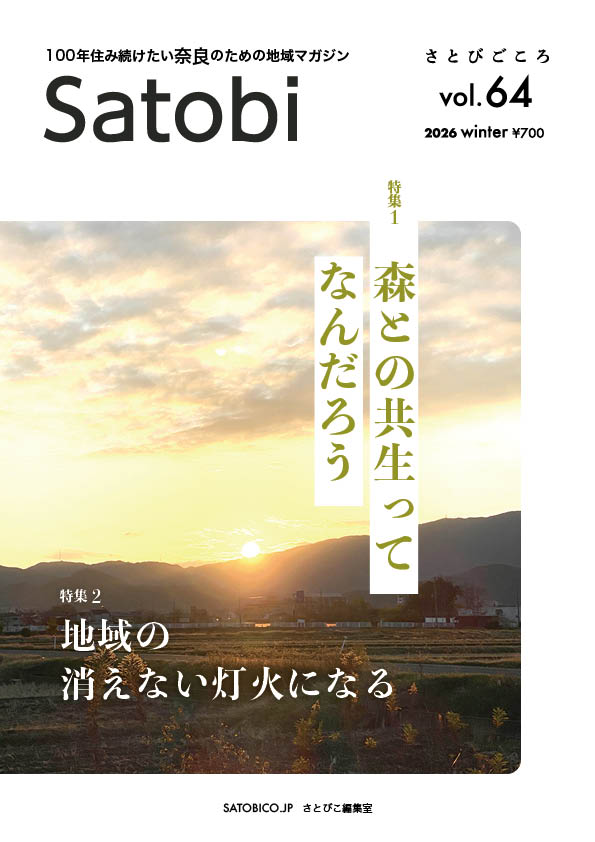お盆あけからそのまま週末に続く今年は、長期のお休みになった方もあったかもしれません。逆に、まさにかき入れ時とお商売に精を出される方、雑草の勢いに負けず雨不足にも負けず農地で汗する方、いろんな過ごし方をされたことと思います。
あなんは、「混み合う時期には家で静かに」をモットーとしており(人の多いところは全く苦手です)、読書や調べものをしながらベランダと仕事部屋と畑を行き来して過ごしています。
お盆というと、明治生まれのおばあちゃん子だったわたしは、祖母が迎え火をしてくれたのを毎年のように思い出します。みなさんは、おガラってご存知ですか。お盆が近づくと、商店の店先に乾燥させた植物の茎が並びました。それが麻だったということを、大人になってから知りました。
日が暮れると、家の中庭のいつもの場所で祖母がおガラを焚きました。「お父ちゃんが帰ってくるよ」というのです。
父はわたしが生まれてから一年たたない33歳ときガンで他界していました。祖母にとっては、息子を失ったことは、それはもうついこのあいだのことのように感じていたことでしょう。わたしは死んだと聞かされてきた父が、あの世から帰ってくるとは信じられず、まわりをキョロキョロしたものです。霊感はないので、父を感じることはありませんでした。でも、暗がりのなかで小さく炎をゆらす迎え火を見るのは好きでした。子どもながらに、おごそかな気持ちになったものです。(今思うと、祖母は淡々としていました。どんなに悲しくても悔しくても、明治生まれの祖母はいつも粛々と耐え、淡々としていました。今さらながらに、祖母を尊敬します。)
お盆。盆おどりや花火大会、夏祭り。夏休みならではの楽しい出来事がたくさんありました。
お盆というのは仏教の行事。祖母はその間だけ仏壇から位牌を出し、ひな祭りのときと同じ段を設置して、祀りました。周囲には、鴨居から吊るす提灯や、足のついた提灯がかざられ、お盆の期間というのは、お正月やひな祭りのように、特別な時なのだとわかりました。親戚の出入りも増え、子供にとってはちょっとハイになるひととき(長男の嫁だった母は、亡くなった夫の代わりに何かと役目を引き受けながらも嫁の立場であることは変わらず、大変だったかもしれません)。お坊さんは、この時期、バイクにのって街を駆け巡っておられました。わたしの家でもお坊さんをお招きしました。お坊さんは特別なお客さまでした。
このようにお盆といえばお寺なのですけど、先祖の霊をとむらうというのは仏教よりも神道よりも前から、人類がやってきたことなんですね。
ホモサピエンス以前の、ネアンデルタール人だって、洞窟に遺体を埋葬して花をたむけたそうです。縄文時代の中期や晩期では、お祭り広場の大事な場所に墓石(と言っていいんでしょうか)を並べていました。亡くなった人も、役目を終えた道具や食べものも、魂があると考えていて、祀っていました。そのような祭祀が、神道に受け継がれたと考えると自然に納得できます。火は霊(ヒとも読まれます。ふつうはレイですが)に通じていて、火を見ていると癒されたり、直感が冴えるような気がしますよね。焚き火に魅力を感じるのは、きっと、魂が喜ぶからではないでしょうか。
わたしは父母ともに出雲出身で、夫の家は父方が大分県、母方が奈良県です。狭い日本であれば、祖先をたどればどこかで共通のルーツを持っていてもおかしくはないかもしれません。そして連綿と、仏教が日本に来るよりもはるかに昔から、祖先の、さらなる祖先に祈りをささげるときがあったはずです。今でいうお盆という風習ではなかったとしても、おそらくそのときも、迎え火と呼んだかはわかりませんけれど、火を焚いていたんじゃないかなあと、勝手に想像しています。
おガラには、そんな文化が引き継がれていたのだと思います。
お盆が近づいても、おガラが売られているのを見かけなくなりました。また、集合住宅で暮らしているとベランダで火をたくことはできません。せめて、蝋燭の火でも見つめながら、先祖のことを考えてみましょうかね。そしてつい80年前には、わたしたちの世代を守るために命をかけてくださった方々のおかげで(そもそも命をかけなくてはならない事態を引き起こした事情については、これからますます明かされていくかもしれませんけれど、そうであったとしても直面した困難に立ち向かってくださったおかげで)今があることを、わたしたちは一生、そして次世代までも、忘れることがあってはならないでしょう。もう、21世紀には絶対にあってはならないこと。あたらしい時代を迎えていきたい。誰かが企てた争いに、名もなき人たちが巻き込まれる時代を卒業しましょう。わたしたちの世代のミッションです。
こうして生かしていただいて、ありがとうございます。どうしても、自分の父母のことをまず思ってしまいます。わたしが生まれる前の、まだ父が発病する前の、若い父母の写真があります。兄がよちよち歩きの足で、二人の間に立っています。その写真に語りかけました。ありがとうございます。セイコも年を重ねましたけれど、いつまでも健康で幸せに生きることが二人の何よりもの願いだと思いますので、それは今のところ、まちがいなく叶えています。どうか、これからも見守ってください。
わたしは、日本人らしい風習というものを若いころは軽視していました。それよりも、興味をそそられることや、追われる仕事のほうを意識してばかりいました。でも、そんなことをしていたら、風習は消えてしまいますね。時代とともに、スタイルが変わったとしても、本質的なことを引き継ぐことはできると今は考えています。もしかしたら、現役を少し退いたわたくしのような世代が、次の世代のためにも振り返り、伝える力を持つことが大切なのかもと思ったりします。若い頃って、時間的にも精神的にも多忙で余裕がありませんものね。
「なぜか知らないけど昔からこうするのよ」ということには、意味があるはずで、その意味を振り返ってみるのは、大きな学びになります。「なぜか知らないけれどこうする」という行事の形になっているからこそ、継承できたのだと思うのです。難しいことまで覚えなくてはならないかったら、どこかで途絶えていたかも。行事にたくすことで、本質の灯火が消えずにすんだのでしょう。遅まきながら、これからはさらにもっと、日本人になれるように年を重ねていきたいと思っています。
今日もSATOBICOのブログにお立ち寄りくださり、ありがとうございました。また次の更新でもお会いできたら嬉しいです。
おガラ
おガラは、表皮を剥いだ麻の茎を乾燥させたもの。古来から麻は清浄な植物とされ、神社のしめ縄などにも使われ、燃やすとその空間も浄められると考えられてきました。麻は日本の風習によりそってきた植物なんですよね。
 写真:こちらより
写真:こちらより
お盆の迎え火と送り火
お盆の始まりと終わりに、自宅の玄関先や庭先などで火をたく行事。おガラで穢れのない空間を作りだす意味もあるそうなので、「穢れを祓う」というのは神道的ですね。お盆行事として定着したのは江戸時代だそうです。
迎え火は先祖の霊が迷わず自宅へ帰ってくる目印。送り火はあの世へのお見送り。
花火
慰霊や疫病退散を願う儀式
麻の文化も、戦後に失われたもののひとつです。あなんは、麻を知れば知るほど、かつて日本のどこでも栽培されていたものがなくなってしまったことが残念に思われます。正々堂々と栽培でき農業振興にもなり、生活に役立つ日がくることを願い、祈ります。