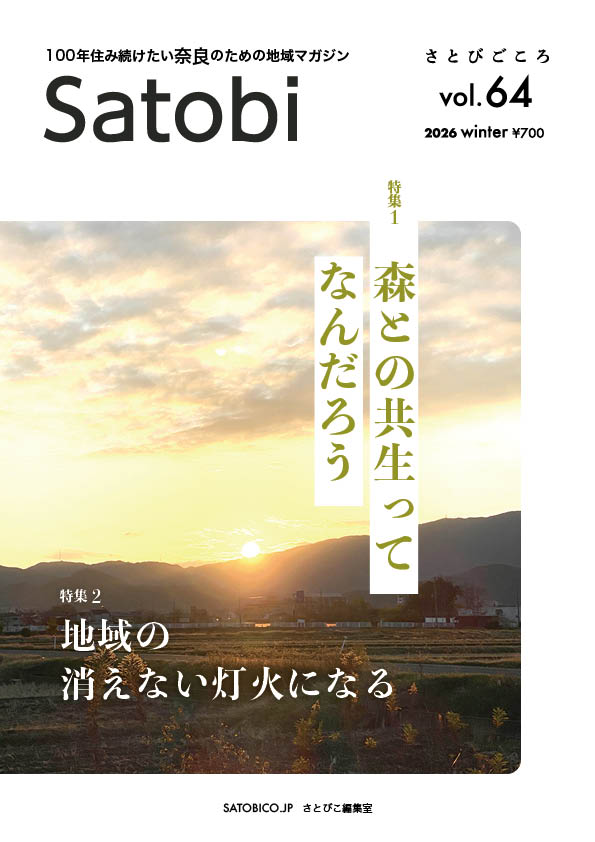日本人は、これまでたくさんの木を使ってきましたね。縄文人も、栗の木を使って建物を建てていました(三内丸山遺跡等)。奈良の都も木の都。江戸時代も、戦前も、燃料や建材として木を使ってきました。それでも、日本が砂漠化しなかったのは、植えてきたからです。
なにしろ、スサノオノミコトからして植林を進めていたのですから、日本人は根っから植林気質のはずなのです。木を切り過ぎると災害が起こりやすいという経験則があり、森を守るために立ち上がる人がいつの時代にもいたのですね。木の伐採というのは、自然からの収奪なのですけど、そのかわり、植林もセットで行われれば森林は持続します。
伐採は一瞬で、植林した苗が育つには50年も100年もかかるので、伐採が先行しずぎると環境破壊に。そのバランスが大事なのでしょう(今、他県でいくつもの山がメガソーラーになってしまっていますが、これをどうやってバランスをとったらいいのでしょうか)。
人間の現役期間は40年から長くても60年くらいなので、木の一生よりは短い。地球と比べたら一瞬。だから、先人からの言い伝え(経験則)を尊重しないと、自分の代の、自分の頭だけではわからないことがあるはずなんです。戦後は、それが「発展」とか「開発」などのもとに、消えていったと思いませんか。
でも、そうなると今度は「再生」しようとする人たちが現れてくるのです。再生は、開発よりはゆっくり進みますから、一夜にして効果が出るものではありませんけど、季節がめぐり、年月がたつと生まれ変わったように景観が変わったりします。開発のための技術が進めば進むほど、再生ための行いも広まっていってほしい。
野菜を収穫したら、また植えますよね。スパンは長いけど、木を切ったら植えたんです(あるいは切らずに更新も)。これからは、開発したら、再生です。
と、思うものですから、さとびは毎号「大地の再生」を連載しています。
あなんが昔からのご縁でつながっている西尾和隆さんが、今や大地の再生士として活躍されており、実態に近いところで取材できるため、連載をお願いしています。他にも再生的な行いは広まりつつありますし、心のエールを贈りたいことに変わりないのですけども、知らない人よりは直接知っている人を取材したほうが責任をもってお伝えできるかと思うので、さとびの場合は西尾さんといっしょに記事づくりをしています。
再生を施した場所が、本当のところ、どうなっていくのか。また、すでに再生された場所が、過去はどうだったのか。そういうことを肉眼で見ることができるのが「地域」の良さだと思うんです。北海道や九州や、外国や、遠くで起こっていることも視野に入れないといけませんけど、あくまでも「じゃあ、自分たちはどうなの?」と考えるときに、参考になるのは、「なんなら見に行ける」地域のできごとではないかと思います。全体と局所。両方見ましょう。
で、いつまでたったら、見出しの話になるの?とお思いのあなた。これからです。
3月の雨まじりの日、陽楽の森で大地の再生活動があると聞いて、行ってきました。陽楽の森については、さとび読者さんはご存知のとおりです。もともと住宅開発からもれて取り残された里山を、所有者である谷茂則さんが「みんなに来てもらえるような場所に。森が喜ぶ場所に」ということで長年にわたって奮闘されているスポット。(その奮闘ぶりは、さとびの連載「十四代目林業家ドタバタイノベーション奮闘記」をご覧ください。次号で、なんと、30回目!)
初回はこちら(時間がたっぷりあるときに、クリック推奨)
近々、ここ陽楽の森の中にカフェができる予定です。市街化調整区域とのことで、いろいろ難問があったと聞いています。苦労が実って、工事(開発)が始まります。


「森が喜ぶ」ということと「開発」は、どうしても相入れないところがでてくるのでは?と、わたしはこの動きに注目しているところです。何かにつけて、避けてはとおれないところが、どんなふうに決着してくのでしょうか。
カフェの計画が進みつつある一方で、大地の再生活動が昨年から続いてきました。陽楽は、セブンの森に採択されていますので、その一環でもあるようです。

 法面と平面が接するところが大地の再生では大事なポイントです。ここが詰まると、山全体が窒息すると西尾さんは言います。逆に、ここに水と空気の通り道を作ることが再生につながります。
法面と平面が接するところが大地の再生では大事なポイントです。ここが詰まると、山全体が窒息すると西尾さんは言います。逆に、ここに水と空気の通り道を作ることが再生につながります。
カフェは間違いなく素敵な場所になるはずで、個人的にも「行ってみたいー!」と、楽しみなのですけど、肝心の里山が元気を失うようなことがあったら、もとこもないですよね。陽楽は、もう「取り残された」という言い方は似合わない。幸運にも残された、都市に隣接する美しい場所になれる。里山の元気のために、土と水と空気の循環をもたらす大地の再生的な取り組みがどこまで作用するかが重要になってくると思います。
カフェのシンボルツリーになるかもしれないクス(1枚目の写真のはじっこに写り込んでいます)のまわりも、手入れに参加しました。谷さんも、奥さまや息子さんといっしょにやりました。所有者みずから、ご家族で参加されるなんて、いいと思いませんか。
クスはかなり元気を失っている状態なのだそうです(西尾さん)。素人は、明らかに枯れてしまわないと気づけないことが多いけど、「まだ息をしている」とは矢野さん(大地の再生を普及させた方)の言葉。カフェができても、元気でいてほしい。
ここでも段差のある境界線のところを掘って、枝や炭を埋めたいそうです(西尾さん)。

おまけ
知っている人たちにも再会できて楽しい。当日は複数のイベントが同時開催されていて、そのひとつ地域食堂でピザを食べました。

陽楽プロジェクトにおける大地の再生活動は、またどこかでまとめて記事にできたらなあと思います。
西尾さんの次号の連載は、この陽楽ではなくて、コンクリートを剥がして大々的に再生した事例が登場しますよ。お楽しみに。
さとびvol.61 春号は4月10日の発行です。読んでくださいねー。
※このイベントは、陽楽の森をホームに、森づくり、苗づくり、薪や農産物などをみんなでつくる団体「みんなでつくる」(みんつく)さんの取り組みです。
2023年までの西尾さんの活動履歴満載の号はこちら(もう残りわずか!)
さとびごころ vol.54 (2023.summer)特集 奈良でじわじわ大地の再生