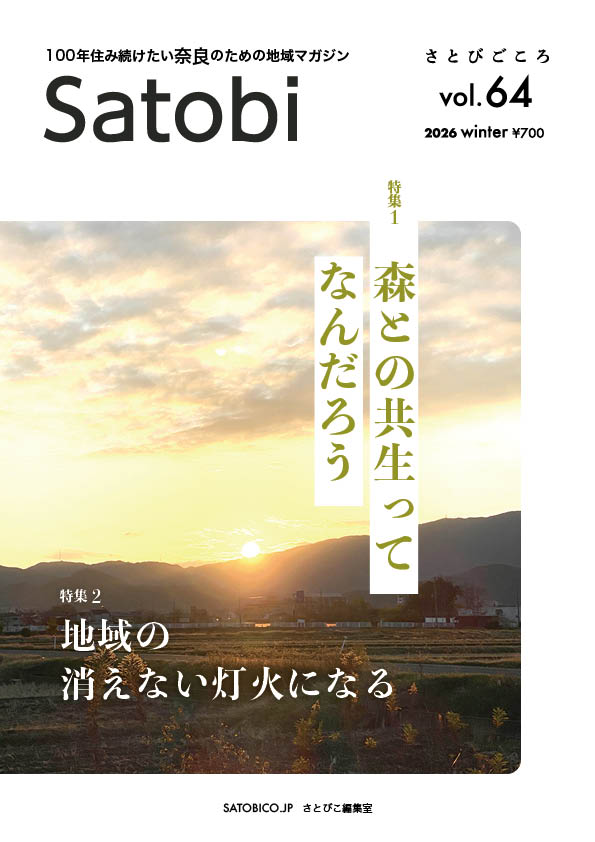御所市の山麓で里山再生のための農に取り組む杉浦農園の背景にある考察を綴っていただく連載「杉さんの里山再生録」9回目になりました。テーマは、「里山の『食』への貢献を考える(2)」。
里山とはよく聞く言葉ですが、なんとなく使われていることも多いかと思います。「里」とは人が住んでいるところ、里に住む人の暮らしとセットになって活用されながら守られてきた「山」が里山です。人を寄せつけない厳しい奥山との中間にある「バッファーゾーン」です。
その里山からどんどん人がいなくなり、生業であった林業農業が成り立ちにくくなっていく現代。「ほんとうにこのままでいいのか」との問いを投げかけ、里山を再生することで生態系豊かな環境を取り戻そうとしているのが杉さんです。それも、現場に立ち、人生をかけて農業に取り組むことによって。
今回は、ドキっとさせられる見出しから始まります。
里山が消滅したら?誇張なしの事実から考える
中山間地域の住民の年齢は75歳前後であり、日本の中でも真っ先に人口が減ってゆく。このままでは、消滅してゆくしかない未来がある。
その後には、大自然が復活するわけではなく、勢いが衰えないソーラー発電開発、田畑、山林、水源の外資による買収が行われ、無法地帯と化し、日本人の心の拠り所となる原風景は2度と戻らない。これは誇張しているわけではなく、最前線で起きている事実と確証だ。
里山のみならず、この国に起きている異変に国民も気づきはじめている。(本文より・太字はSATOBICO)
何の対策もなく里山がこれ以上荒廃していくと、危機的です。さとびの誌上で、現場の最前線に立つ杉さんから、こうした現実を伝えていただけたこと、ありがたいと感じています。
牧歌的な意味だけで里山再生を取り上げたいわけではなく、かなり深刻な現実を踏まえてのこと。里山だけではなく、あちらでも、こちらでも、日本らしさが消え、日本の国土が売られていきます。なぜなのか、ひとりひとりが情報を取り寄せて考えていかなくてはいけないことだという切実さが増しています。里山で暮らしていない(わたしも含めて)奈良県の都市部に住む人たちとともに、共有したいことなのです。
それを踏まえて、杉さんは考察します。里山の「食」への貢献です。
続きはぜひ、さとび春号 vol.61で杉さんの言葉に触れてみてください。
なお、御所で、半農半エックス的な暮らしを望む人を対象とした農業スクールができました。杉さん、校長先生になりました。さとび春号が出回る頃には開校ですが、授業内容によっては開校後にその都度参加できるものもあるようですので、興味のある方はお問い合わせくださいね。
御所から遠い方でも、それぞれのお住まいの周辺で、きっと努力されている方がいます。
自然も人も豊かな未来のために、自然にも人にもやさしい人が。
そんな人といっしょに何か取り組んでみたり、取り組むのが難しかったら参加したり、協力したり、応援したり、おしゃべりしてみたり、何か1ミリでもいい方向へ傾けることは何なりとあるはずだと思うんですよね。身近にそんな人がいない…という方は、杉浦校長先生にコンタクトをとってみてください。幸せの方向を向いて、暮らしていきましょう。
さとび春号 vol.61は4月10日の発行です。
4月10日からは、オンラインショップでもお求めいただけます。
4月中旬からは奈良市内の三つの書店(ベニヤ書店、啓林堂奈良店、たつみ書店)・お取り扱いスポットでもお求めいただけます。
読者メンバーに登録されますと、毎号ご指定のところにお届けします。
定期購読コース
サポーターコース(さとびのコンセプトに共感して応援してださる方)