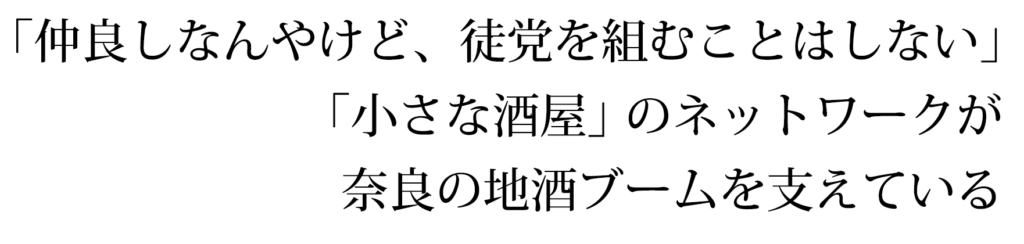この記事はさとびごころVOL.46 2021 summerよりの転載となります。内容は掲載当時のものです。
44号の特集「地酒で味わう奈良2」で執筆していただいた河口充勇教授による新連載。
ブランド力を高めている奈良酒の背景にある地域力を考察していただきます。
日本酒のことを悪く書かないで…と言われた日
2000年春、留学先の香港から一時帰国した際、筆者は、指導教授に連れられて京田辺の蕎麦処を訪れ、そこではじめて口にした滋賀の地酒に大きな衝撃を受けた。酸味と甘みのバランスが絶妙で、それまでに飲んだ日本酒とはまったく別次元のうまさだった。その日を境に日本酒に強く惹かれるようになった筆者は、縁と運に導かれて、2005年からの5年間、大学院時代の先輩とともに京都伏見酒造業の調査研究を行なうことになった。(※1)
※1 藤本昌代・河口充勇『産業集積地の継続と革新-京都伏見酒造業への社会学的アプローチ』(文眞堂、2010年)
この伏見調査に着手したばかりの頃に、ある蔵元から掛けられた言葉が今も忘れられない。
「お願いだから、日本酒のことを悪く書かないでください…」。
この言葉が端的に示すように、当時の日本酒業界は、長期にわたって厳しい逆風に晒されつづけていたのである。ところが、2010年代に入った頃より日本酒業界を取り巻く風向きが劇的に変わった。各種メディアがこぞって日本酒を取り上げ、「おいしいもの」「おしゃれなもの」「世界が認めるクールジャパン」などと喧伝するようになった。
そのおかげで、大学において「酒育」活動に取り組む筆者にとって、日本酒の魅力を学生たちに伝えることが以前に比べて格段に容易になっている。少なくとも今の学生には日本酒のマイナスイメージはほとんどない。先述の蔵元の言葉を筆者が耳にしたのはわずか15年ほど前のことであるが、まさに隔世の感がある。
 「酒育」活動の一環で訪れた梅乃宿酒造「蔵開き」(2019 年10 月)(前列右端が筆者)
「酒育」活動の一環で訪れた梅乃宿酒造「蔵開き」(2019 年10 月)(前列右端が筆者)
注目を集める奈良の地酒
このように追風を受ける近年の日本酒業界にあって、奈良の地酒は特に注目を集める存在になっている。昨年10月、近畿経済産業局が「『地域ブランドエコシステム』構築を目指す10のモデル」を発表し、その一つに「奈良酒」を指定した(日本酒としては唯一)。その翌月には、『日本経済新聞』に「奈良の酒蔵 光る『稼ぐ力』」と題された記事が掲載され、奈良の若き蔵元たちの革新的経営にスポットライトが当てられた。また、創刊より30年にわたり日本酒の魅力を発信してきた人気雑誌『dancyu』において今年3 月に日本酒特集が組まれ、奈良のさまざまな地酒が日本酒の「深化」を示す事例として取り上げられた。
このように、奈良の地酒は時代の追風を受けて急激にブランド力を高めつつあるが、そこに至るまでの道程は決して平坦なものではなかった。
戦後の高度経済成長期(「規模の経済」がモノを言った時代)、日本酒は慢性的に供給が不足しており、多くの中小酒蔵が大手メーカーの下請け生産(業界用語では「桶売り」)を担った。ところが、日本酒需要が頭打ちとなる1970 年代半ば以降、「桶売り」は急激に意味を失い、廃業を余儀なくされる中小酒蔵が後を絶たなかった。
その一方で、1970 年代後半にはじまる「地酒ブーム」(新潟から全国へと波及)のなかで、「規模の経済」とは一線を画する新しいビジネスモデル(個性や限定性、物語性、地域性を重視する酒造り)が生まれ、「小さな酒蔵」の生き残る道が開かれた。この道が確固たるものになるのは、十四代(山形)に代表される「蔵元杜氏(※2)」第1 世代が台頭する1990 年代後半以降のことである。「小さな酒蔵」が県内各地に散在する奈良酒造業の歩みもやはりこうした時代の流れとともにあった。
※2「蔵元」(経営責任者)兼「杜氏」(製造責任者)を意味する。
地酒ブランドの成長メカニズムとは
地酒ブランドの成長メカニズムを考える際、当然ながら、各蔵の自助努力は第一に考慮すべき要因であろうが、それ以外にもさまざまな外的要因が介在しているのではないか、と筆者は考える。おそらく、外的要因は地域ごとに「似て非なる」ものであり、新潟には新潟の、山形には山形の、そして奈良には奈良の「何か」があるにちがいない。筆者自身の奈良地酒調査を通して見えてきた一つの仮説は、1990 年代にはじまる「小さな酒蔵」と「小さな酒屋」の地域に根ざした協力ネットワークこそが奈良における「何か」ではないか、ということである。
本紙第44号の特集「地酒で味わう奈良2」に掲載された拙稿「奈良の地酒とともに紡がれた小さな酒屋の大きな物語」では、その端緒となった登酒店の登のぼりかずしげ和成さんと梅乃宿酒造の吉田暁(あきら)さんの「幸福な出会い」を描いた。これにより、1993 年に「無濾過生原酒」(※3)と呼ばれる新しいタイプの酒が送り出されることになった(県内初、全国レベルでも先駆的なケース)。
前掲の拙稿にあっては、「小さな酒屋」としての登さんの歩みを紹介するものであったため、その一大転機をなした「無濾過生原酒」との出会いに焦点を置いたが、奈良の地酒全般の歩みを考えるとなると、「無濾過生原酒」そのものではなく、それを一つの契機として構築された酒蔵と酒屋の協力ネットワークのほうがいっそう決定的な意味をなしたのではないか、と筆者は考える。具体的には、梅乃宿の販売促進を目的として、登さんを中心に奈良の「小さな酒屋」有志(約10名)によって結成された暁会(あかつきかい)(※ 4)がそれに当たる。
※3 濾過、加熱殺菌、加水をしていない搾りたての酒のこと。
※4 名称は吉田暁さんの名前に由来している。
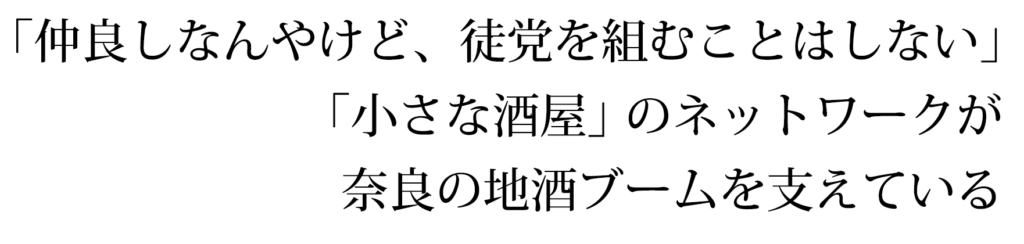
協調しつつも個々で動く人間関係図式
暁会そのものは梅乃宿の成長とともに役目を終えていったものの、そこで構築された協力ネットワークはその後も機能しつづけ、前掲の『日本経済新聞』記事や『dancyu』日本酒特集で取り上げられた多数の地酒ブランドの成長を支えてきた。なかには、廃業寸前まで追い込まれた「小さな酒蔵」がこの協力ネットワークの支援によって復活を遂げたケースも含まれている。この協力ネットワークの特性について登さんはこう語っている。
「仲良しなんやけど、徒党を組んでみんなでワーッと行こうというようなことはしない。時々共闘するけど、でも基本は個々で動いている。…中略… もしかしたら、後ろ向いて僕の悪口を言うとるやつがいるかもわからへんけど(笑)、でもやっぱり刺激もあるし、話も合うし、大事な関係なんです」。
そこに見られるのは、自立性と協調性を兼ね備える、「自己組織化」された人間関係図式であると言えるのではないだろうか。
本連載(2 年計画)では、暁会に参加した「小さな酒屋」の物語を描くことにより、1990 年代以降に奈良の地酒がいかにしてこの土地ならではの環境のなかで育まれてきたのかを振り返るとともに、これからどのような道を進んでいくことになるのかを展望したい。
 1990 年代、「小さな酒蔵」と「小さな酒屋」の、地域に根ざした協力ネットワークが胎動した。顧客を梅乃宿酒造に案内する登酒店・登和成さん(右から3 人目)。
1990 年代、「小さな酒蔵」と「小さな酒屋」の、地域に根ざした協力ネットワークが胎動した。顧客を梅乃宿酒造に案内する登酒店・登和成さん(右から3 人目)。
さとびごころVOL.46 2021 summer掲載
文・河口充勇(帝塚山大学文学部教授)