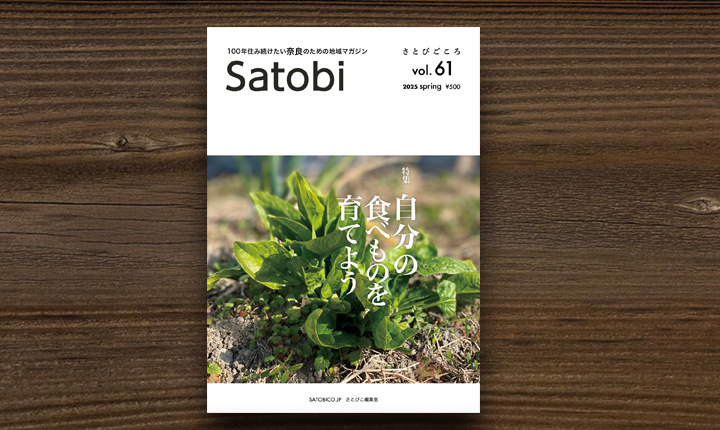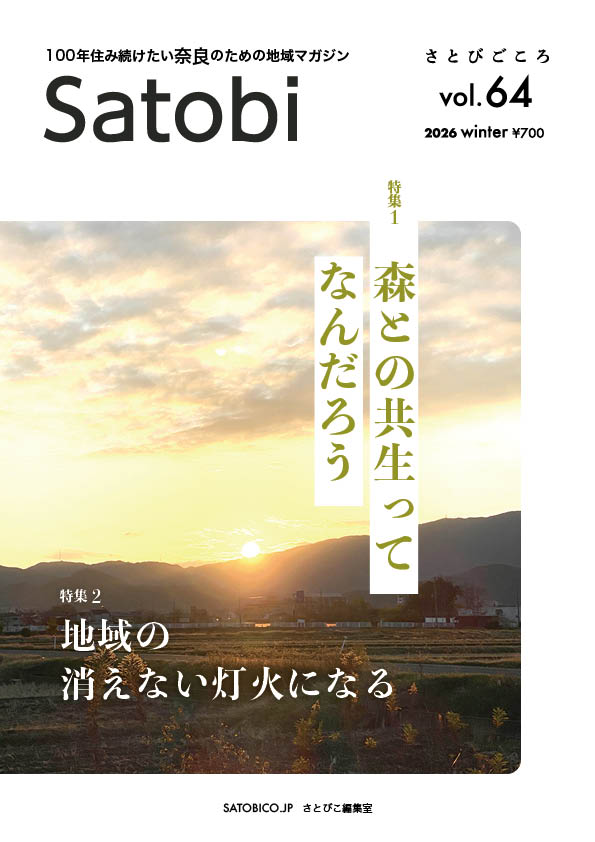ひとりでさとびづくりを続けて8年目(その前の段階を含めると、今年で15年め)。誰に届いてくれるのか自信もなく始め、これはただの自己満足活動なのかと思ったことも数え切れませんが、とにかく届けたい、残したいという思いに導かれながら続けてきました。
それでも、続けていますと、ときどきびっくりするようなことがあります。先日は、故郷の奈良県にもどって耕作放棄地を引き受けながら新しい活動を始めようとしている方からのご相談をうけました。
耕作放棄地の仕立て直しに着手後、草刈り迄は一旦終わりました。ここからが土壌改良も含めた今後の農業モデルの実験に入ります。川(農地を貫いている川)の水質検査が1週間ほどで出ますので、地域性を出したブランディングも含め知恵を絞って行こうと思います。阿南さんの培われたセンスを拝借したく、一度zoomでミーティングは可能でしょうか?
と、事前にオンラインでプロジェクトの概要を説明いただき、「一度現地を見てほしい」とのこと。世間はゴールデンウーク中でワクワクだったと思いますが、わたしも、どこかへ遊びに行くのよりもずっとずっとワクワクする気持ちを抱きながら行ってきました。
わたしは、行政のことも法律のことも土木のことも、何一つ専門家ではありませんし、農業に関してもママゴトのような家庭菜園をしているだけです。ただ、地球のことを地域に落とし込んで考えたときに、どんな方向性がいいのだろうか?ということだけは考え続けてきだので、こんなんでよければどうぞ、という気持ちで行ってきました。
 どこにでもありがちな砂防堰堤。教科書的な言い方をすると、「上流からの土砂を一時的に貯めて徐々に下流に流す施設。土石流による災害被害の軽減、川底の削り止め、川の勾配を緩やかにするなどの役割」と言われていますが、川の流れが澱んでいるのが現実です。Hさんは、「ないほうがいい」と考えています。(とはいえ、おいそれと撤去はできませんが)
どこにでもありがちな砂防堰堤。教科書的な言い方をすると、「上流からの土砂を一時的に貯めて徐々に下流に流す施設。土石流による災害被害の軽減、川底の削り止め、川の勾配を緩やかにするなどの役割」と言われていますが、川の流れが澱んでいるのが現実です。Hさんは、「ないほうがいい」と考えています。(とはいえ、おいそれと撤去はできませんが)
 護岸擁壁。川の侵食から岸を守るためとされています。昔ながらの石積みと近代的なコンクリート。どちらも劣化が見えます。ここは大地の再生の出番ではないでしょうか?河川管理を担当する行政局との連携が必要ですが、改修の機会があれば、ぜひ川の呼吸をとりもどす手法を取りれてもらえないかなあと思いました。Hさんにミスター大地の再生士・西尾さんを紹介することにしました。
護岸擁壁。川の侵食から岸を守るためとされています。昔ながらの石積みと近代的なコンクリート。どちらも劣化が見えます。ここは大地の再生の出番ではないでしょうか?河川管理を担当する行政局との連携が必要ですが、改修の機会があれば、ぜひ川の呼吸をとりもどす手法を取りれてもらえないかなあと思いました。Hさんにミスター大地の再生士・西尾さんを紹介することにしました。
まだ詳しくはお伝えできないのですが、水質や土壌を美しく保ち(=景観や環境をおびやかす土地利用を防ぎながら)、農業を軸に満足な生活が成り立つ仕組みを作ろうとされていました。
周辺には由緒あるスポットもあり、観光地としての可能性もチェックされ、かたや志の通じる人が集まってこれるような構想もお持ちでした。すでに、県外から移住してこられる方が数名、決まっているそうです。
中心となっている人がこの地で生まれ育ったHさん、その盟友であるYさん(こちらは関東の方)です。Hさんは20代のころから海外で起業、その経験から水質浄化の必要性を感じ水をテーマに事業を展開、Yさんとの出会いがあり、そして「水」の延長線上に農業がありました。
今、日本の農業はあと5年と言われています。
農業機械を動かす燃料も肥料も外国からの輸入だのみ。何かの事情で輸入がストップするか、ストップしなくても高騰してしまうとたちまち危機に瀕するという状況にあることは、鈴木宣弘氏をはじめとした有識者から、さかんに警鐘が鳴らされているところです。政治に期待している猶予はなく、意思ある人が行動する必要があります。
そんな中でも、さとびつながりの人たちの中には、粛々と信じた未来にむかって行動している人たちがあり、いつもそのあたりをお伝えしようとしています。Hさんたちも、そうなのかもしれません。
本気でやるならば、故郷に根ざして取り組むしかないと決断したそうです。これまでの経験を、実際の形にしていくための実験でもあります。成功が約束されているのではなくて、成功を「創造」していく取り組みです。事業を経験されており何もないところからの裸一貫ではないところが頼もしいのですが、農業の経験は限りなくゼロ。地元のおっちゃんに教えをうけながら、草刈りでもなんでも、自ら汗をかいてチャレンジされています。
Hさんの幼い頃をご存知である地元の人たちからは、歓迎されています。さすがはUターンです。すでに数ヶ所の農地を頼まれておられました。あるところでは土壌改良済み。あるところでは苗の定植済み。また、あるところでは、稲づくりも始まろうとしていました。
午前から午後にかけてご一緒してみて、これからの成功は「経済的に大きな結果を出すことよりも、もっと求道的なものになるのではないか」とおっしゃっていたのが印象的です。その通りだと思います。
阿南さんの曇りのない目で見ていただき可能性を見出せたのは我々にとって日々のモチベーションをより高いものにする大きな刺激です。水は清濁合わせながら流れますが、汚す人間がいなければ自然に清流に戻ります。しかしながら我々の社会は人が自然を破壊しているのが現実で、本事業においては清濁合せ飲みながらも前進しなければならない時もあります。その点で我々の使命は大きいと勝手に受け止めており、志を共にしたより多くの方々との連帯が重要です。その点においても方向性のブレない阿南さんの視点と気付かせる能力は不可欠だと改めて感じました。今後とも一緒にワイワイしながらも真剣に取り組んで行けたら幸いです。
一人ではできないことは、仲間といっしょに行動していく必要があります。そしてよくあるのが、何かと「人間だもの」的な問題も起こりがちで、なかなか難しいものです。でも、志をともにでき、プロセスはどうあれ地域が美しく保たれて活気が生まれる夢を共有できれば、その難しさも乗り越える道が見つかるのではと思います。
このプロジェクトの全貌をお伝えするには、Hさんの今に至る布石となる取り組みから説明する必要がありそうです。さとびではページが足りない予感がしますので、ブックにできたらいいなあと思いました。
まだまだ、出会ったばかりですし、プロジェクトも始まったばかり。ゆっくりと信頼関係を深めながらこれからの人たちにとってのモデルとなるプロジェクトになるよう願って、継続して訪ねていきたいと思います(すでに次の予定を調整中)。そして、いつか読者のみなさんと、ここで楽しいイベントができたらいいなと思います(わたしのことですから、ちっちゃいやつ)。
ご案内くださったHさん、Yさん、お世話になりました。ランチごちそうさまでした。ありがとうございました。
さとび春号、すでに残り少なくなりましたがオンラインショップで発売中です
さとびごころvol.61 (2025 spring)増ページ編集32P
特集 自分の食べものを育てよう。
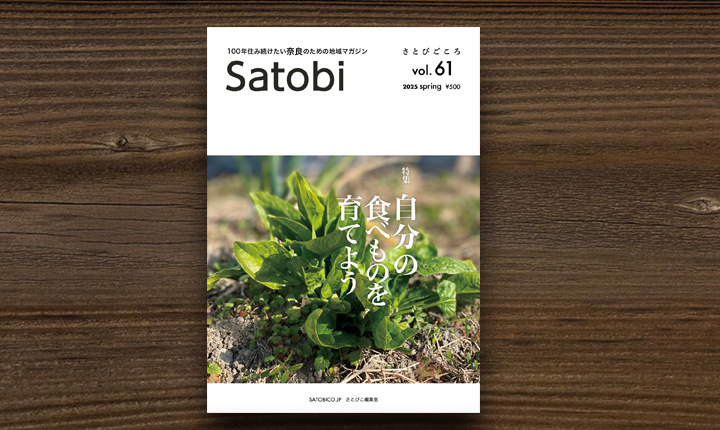
大地の再生特集はこちら
さとびごころ vol.54 (2023.summer) 特集 奈良でじわじわ大地の再生