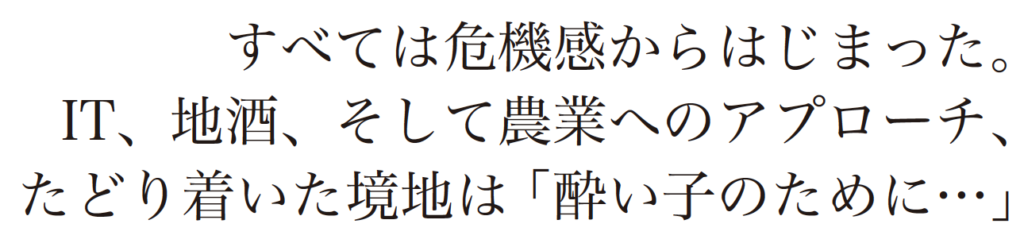この記事はさとびごころVOL.48 2022 winterよりの転載となります。内容は掲載当時のものです。
奈良の地酒ブランドの持続的成長を支えてきた地元の「小さな酒屋」の物語。
今回は、西の京地酒処きとらの店主、木寅伸一さん(1962 年生)の物語です。
奈良でいち早くネットビジネス
1980 年代半ば、大学卒業後に家業の酒販店経営に携わるようになった木寅さんは、早々に父親(創業者)から「これからはお前がやれ」と後を託された。当時の酒販業界では、近い将来に従来型の経営スタイル(宅配型)が立ち行かなくなるとの危機感が高まっており、木寅さんも時代の流れを敏感に察知していた。「酒販店情報ネットワーク」(1984 年設立)というグループがあるのを知って入会し、その「知恵袋」的存在であった野端格さん(大阪府高石市の酒販店経営者)の薫陶を受けた。
「これからの時代は、まず情報が動き、カネが動き、そして、モノが動く。これを理解できない酒屋は生き残れない」という野端さんの言葉に衝撃を受けた木寅さんは、酒販店情報ネットワークが展開していたさまざまな共同事業、たとえば、宅配機能の高度化(大手百貨店との提携によるカタログ販売など)、店売り機能強化のためのIT 化(ソフトウェアの共有、販売データの分析など)を積極的に取り入れて、自らの経営環境の改善に努めた。
奈良県下にあって木寅さんは酒販店情報ネットワークの古参メンバーの一人であり、その会員拡大に大きく貢献した。自ら勧誘のためのDMを作成し、県内各地の同業者に送付したところ、本誌第44号で紹介した登酒店の店主、登和成さんから問い合わせの電話が掛かってきた。その後、登さんを中心とする奈良の同業者グループが入会することになるが、そのなかには前号で紹介した酒のあべたやの店主、村井誠さんも含まれていた。1990 年頃のことである。IT 化をめぐる木寅さんの迅速な行動は、その立地条件(幹線道路に近く、早くから酒類ディスカウントの出店が相次いだ)ゆえに危機感の高まりが早かったということと大いに関係があるだろう。
木寅さんのIT へのアプローチは、21世紀を迎える頃に新たな局面を迎える。その頃、目と鼻の先にある「世界遺産」唐招提寺の観光客向けに自作の「お品書き」を配り、店頭・電話・FAX 等で注文を受け付けていた。そんなある日、店頭にやって来た20代前半の女性がつぶやいた。「インターネットで注文できないんですか?」と。この言葉が彼の心を激しく揺さぶった。「時代についていけていない自分がわかりました。すぐにアスキーの『インターネットでお店やろうよ』を買い、自分でホームページを立ち上げました」。
その後、木寅さんは、ネットビジネス関係のさまざまな異業種交流会に参加するなどネット販売のスキルアップに努めた。暗中模索のなかで始まったネット販売であったが、「結果」が表れるまでに長い時間を要しなかった。
「地酒、教えてください」
2000 年代初頭の時点では、きとらはまだ地酒専門酒販店ではなかった。すでに本誌で紹介した登酒店やあべたやとは異なり、きとらにおいてはIT へのアプローチが地酒へのアプローチに先んじた。
ネット販売に着手したのと同じ頃、木寅さんは、酒販店情報ネットワークの活動の一環として地元西ノ京地域で市場調査を行ない、その結果、唐招提寺を訪れる観光客向けに「地酒を売る」というアイデアを得た。
「それまでは登さんたちに『地酒なんかやめて、缶ビール安く仕入れて売りましょうよ』って言ってました。地酒のことをボロクソに言うてましたから、あべたやさんなんかは僕のこと大嫌いやったと思います(笑)。それが急に『地酒やりたいから、教えてください』って言い出したもんやから、えらいびっくりされました。登さんとあべたやさんは僕の『大先生』。彼らに教えてもらった通りにやりました。むちゃくちゃ売ったので、『お前、売りすぎや』って登さんに怒られました(笑)」。
登さんや村井さんと同様、木寅さんにとっても梅乃宿酒造は特別な存在であった。「その頃は『梅乃宿ホテル』って呼ばれてまして、仕込みの時期には蔵人さんたちの部屋で泊まらせてもらいました。そこで見聞きした話をお客さんたちにすると、すごく喜ばれました」。
こうして木寅さんも暁会(梅乃宿の販売促進を目的として立ち上げられた地元酒販店のネットワーク)の一員となった。
登さん、村井さんと同じように、木寅さんもやはり酒の会や蔵見学会といったイベント企画、SNS を用いた情報発信などを通して顧客とのコミュニケーションに努めてきた。
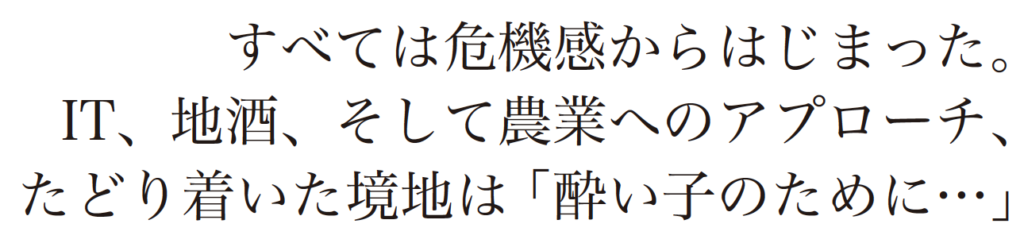
「お米からお酒をつくりたい」
登さんによれば、木寅さんの最大の特徴は「とにかく何でもやってみるところ」にあるという。それは、2000 年代末にはじまる農業(酒米作り)へのアプローチにおいて最も顕著に表れている。きっかけは、木寅さん主催の蔵見学会に参加した常連客の女性がつぶやいた、「お米からお酒をつくりたい」の一言。これがまた木寅さんを新たなチャレンジへと突き動かすことになる。
もともと木寅家は兼業農家であり、農地を所有していたものの、すでに離農して久しく、すぐに自前で対応できる状態ではなかった。そんな時に強力な「助っ人」が現れた。きとらの常連客である地元農家から酒米の「山田錦」を栽培しているとの話を聞かされた。まさに「渡りに船」であった。
その後、酒の会の常連メンバーと協議を重ね、「自分たちのお酒造りプロジェクト」を発足させた。2014 年のことである。木寅さんとプロジェクトメンバーは、地元農家のグループ「グリーン興福院の里 垂仁酒米倶楽部」のサポートを受けながら、垂仁天皇陵近くの田圃で「山田錦」を栽培し、梅乃宿に醸造を委託した。こうして生まれた「自分たちのお酒」には、「垂仁の郷」という名称(きとらのPB)が付されることになった。当初、木寅さん自身は1 年だけのつもりであったが、多くのメンバーの「高揚感」を目にして、プロジェクトの継続に踏み切ることになった。
 「自分たちのお酒造りプロジェクト」の田植えイベントに集まったメンバー
「自分たちのお酒造りプロジェクト」の田植えイベントに集まったメンバー
今日、酒販店が主催あるいは共催する酒米作り・酒造りの取り組みはさほど珍しいものではないが、「自分たちのお酒造りプロジェクト」は、その規模と体験企画の多さという点で際立った存在である。2021 年においては164 名がプロジェクトに参加し、約2000 キロの酒米を収穫した。メンバーは、春の籾まきにはじまり、田植え、草引き、案山子作り、村祭り、稲刈り、脱穀、杉玉作り、蔵での酒搾り、完成祝賀会に至るさまざまな体験企画に参加するとともに、参加費として定められた本数を買い取ることになっている。
危機感からはじまったIT と地酒へのアプローチであったが、近年の農業へのアプローチを通して木寅さんがたどり着いた境地は「酔い子のために…」。今年2022 年に還暦を迎える木寅さんは、常連客(仲間)とともに大切に育ててきた「自分たちのお酒造りプロジェクト」を自らのライフワークと考えている。
 木寅さんとプロジェクトメンバーの思いが詰まった「垂仁の郷」
木寅さんとプロジェクトメンバーの思いが詰まった「垂仁の郷」
 「垂仁の郷」完成祝賀会でのライブ演奏、ギター担当の木寅さん(左から2 人目)
「垂仁の郷」完成祝賀会でのライブ演奏、ギター担当の木寅さん(左から2 人目)
さとびごころVOL.48 2022 winter掲載
文・河口充勇(帝塚山大学文学部教授)